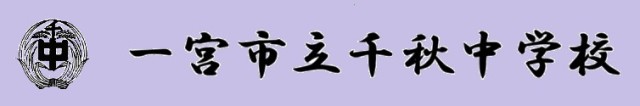3月6日(水)第77回卒業式
- 公開日
- 2024/03/06
- 更新日
- 2024/03/06
校長室から
3年生は,力を振り絞って,さわやかに卒業していきました。卒業生のこの先に幸多かれと祈るばかりです。
保護者の皆様,地域の皆様に感謝申し上げます。
以下は,式辞の抜粋です。
========
この春に、晴れて卒業する一九四名の皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんは、今日この時を、また新たな起点にして、ますます自分自身を輝かせ、さらに生き抜く力を身に付けていくと信じています。
さて、能登半島地震では、受け入れがたいことやものを、受け入れざるを得ない苦しさが、心を突き刺しました。そんな中、避難所で「何日かぶりに水が出た。二次避難により水が出る、勉強ができる。」といった小さな希望に光を感じる生徒たちの、現状を受け入れていこうとする姿に、私たちは何をすべきか、今何気なく流れる環境や時間に対して、どのように向き合っていくかを、考えさせられました。
ありふれた日常の捉え直しや、生きることの尊さ、生き抜くための力強さの必要性を、目の当たりにしました。振り返ってしまう思いを封印するのではなく、思い出される記憶を、自身を奮い立たせる力に変え、前へ前へと進む歩みをやめないことの大切さを痛感しました。
新幹線運休による修学旅行延泊は、そういった意味では災害でありました。状況を理解し、一人ではないことを心の支えとし、仲間と互いに気遣い、励まし合って前を向く皆さんに、助けられました。
目標や、先にあるはずの確かなものを、手探りで追い求め続けることの困難さは、いつでも誰でも同じです。
私たちの人生は、これまでの歴史の上に成り立っています。歴史になってきたこと、歴史にしてきたこと、どちらも人の知恵によって生かし生かされ、今なお新たな歴史を作り続けています。
自分を社会に生かすと共に、歴史を作っているという重要な役割を意識し、生き抜いていく強さを持たねばなりません。その強さが、その先の自分の光となり、進むべき道へと、導いてくれるからです。しかしながら、立ち止まって身動きの取れないときもあります。そんなときは、弱さを受け入れてください。そして、それを誰かと共有してください。共有できることも大事な強さです。
昔、子供のころにきいたなぞなぞに、「朝は四本足、昼は二本足、夜は三本足。この生き物は何か?」というものがあります。答えはおわかりの通り人間です。人間は生まれてから自ら動けるようになるまでに、他の動物よりも多くの助けが必要です。自分で立ち上がり、二本足になるといよいよ自立が始まります。三本足は、二本プラス一本と捉えると、何かの助けを得て、自立し続ける様子です。皆さんは、今まさに機能的な自立を果たし、精神的な自立を進めているところです。自ら立って前に進むだけでなく、共に歩む誰かの三本目の足となることが自立の完成形のはずです。そのためには、絶えず、自分以外の誰かと、互いにその存在を意識し合い、認め合わなければなりません。
これまで、九年間の義務教育では多くの基礎的・基本的な知識・技能を身に付け、見方・考え方を高めてきました。そして、この先もその学びは続いていきます。それは、自立をさらに進め、そして「働く」ためです。
「働く」という字を想像してみてください。人偏と「動」動くという字から成り立っています。「動」は、左上の「人が立っている」象形と、左下の「重い袋の両端をくくった」象形、右側の「力強い腕」の象形から、人が重い袋を「うごかす」ことを意味する漢字であるということです。その左側にさらに、横から人が見た象形の人偏がついてこの漢字が成り立っています。
「働く」の「働」の意味は、ただ、仕事をする、稼ぐという意味にとどまらず、他人のために奔走する、有効に作用するといった意味も持っています。すなわち、「何かを成し遂げる行動をし、その行動によって人に利益をもたらす」という意味であります。この意味では、働くことも、目指すべき自立の要素です。
卒業生の皆さん、喜びと困難は、どちらか一方が続くことは少なく、交互に繰り返されます。困難の方が長く続くこともあります。しかし、大きくても小さくても、自分が満足できる喜びを知ると、困難に立ち向かう力がわき、困難を乗り越えると、次の喜びにたどりつきます。目の前に訪れるすべてのことは、自分のため誰かのために生きる舞台です。自分らしく力強く演じ、生き抜いていってください。
生徒たちは、これまで守られてきた義務教育の学校から、様々な風の吹く、社会の入口に向かって出発します。「千秋の子」から「千秋の人」へと、今後ますます自分磨きを続け、さらに大きく成長していくことを祈念しまして式辞といたします。
令和六年三月六日
一宮市立千秋中学校長 内田 正弥