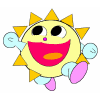思いやりのかたち 1月15日
- 公開日
- 2021/01/15
- 更新日
- 2021/01/15
校長だより
2年生の道徳では、大切な家族にどんなことができるとよいか考えていました。教師が「おうちの人が朝どんなことをしてくれていますか」と問いかけると、「朝ごはんを作ってくれます」「水筒にお茶を入れてくれます」「洗濯をしてくれます」「家族みんなに『行ってらっしゃい』と言ってくれます」など一人一人が家族の様子を思い浮かべて発言をしていました。また、大切な家族のために自分はどんなことができるか問われると「赤ちゃんの世話をしたいです」「自分にやってくれていることをやって驚かせたいです」「ご飯の準備を手伝いたいです」などの声が聞かれました。一人一人が友達の発言を熱心に聞いて、声ではなく拍手で認め合う姿がとてもほほえましく感じられました。
4年生の道徳では、点字ブロックが考案されたお話から、人を思いやるとはどんなことか考えていました。点字ブロックという目に見えるもの以外にも、目には見えにくいことにも想像力を働かせ、声をかけることや手を差し伸べることも大切であることに気付くことができました。それぞれが熱心に自問し、考える姿が印象的でした。
授業を見ながら、今、自分が置かれている場所からは気がつかない、見えないことはたくさんあるということを意識すること、そして「見えていないかもしれない」「気づいていないかもしれない」と想像力を働かせることは大切であると感じました。「音がよく聞き取れないから返事ができないかもしれない」「体がうまく動かないから早く動くことができないのかもしれない」と自分とは違う視点で想像してみること、「誰かが整えてくれるから快適でいられる」「誰かが用意してくれるから使えている」「誰かの声かけで元気でいられる」など、何気ない生活の中にも、たくさんの人に支えられていることに気付くこと、こうした想像力を働かせる余裕をもつことで、感謝の気持ちが生まれ、互いに思いやりの気持ちをつなげることができます。目に見える、見えない思いやりのかたちに気付く力を、これからも大切に育てていきたいと思います。